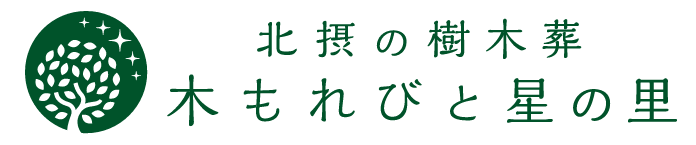お彼岸の墓参り
「彼岸(ひがん)」とは、広辞苑では、
河(三途の川)の向こう岸という意味で、
生死の海を渡って到来する
終局・理想・悟りに至る世界(涅槃)と
書かれてます。
煩悩や迷いのある世界から
悟りの開けた世界へ至ることを指し、
語源は、paramita(波羅蜜多、パーラミタ)と
いうもので、
仏教用語で、「彼岸(パーラム)」
「至る(イタ)」の2つの意味があると
されています。
また、彼岸には、仏道の修行を積む期間と
いう意味合いもあるようで、
古来から仏道の修行を行っていない人も、
この期間、煩悩を払うために西に沈む太陽に
祈りを捧げていたようです。
それは、春分の日と秋分の日の中日は、
太陽が真東から出て真西に沈むこの日に、
沈む太陽を拝むことが西にある極楽浄土に
向かって拝むこととなり、
悟りが開かれるのだと考えられました。
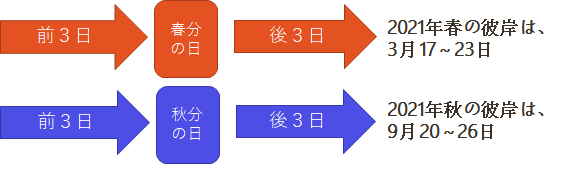
これらのことが、
日本独自の先祖を敬うという習慣と
関係づけられることにより、
この彼岸の期間に、先祖のお墓をまいるという
風習として根付いてきたとされています。